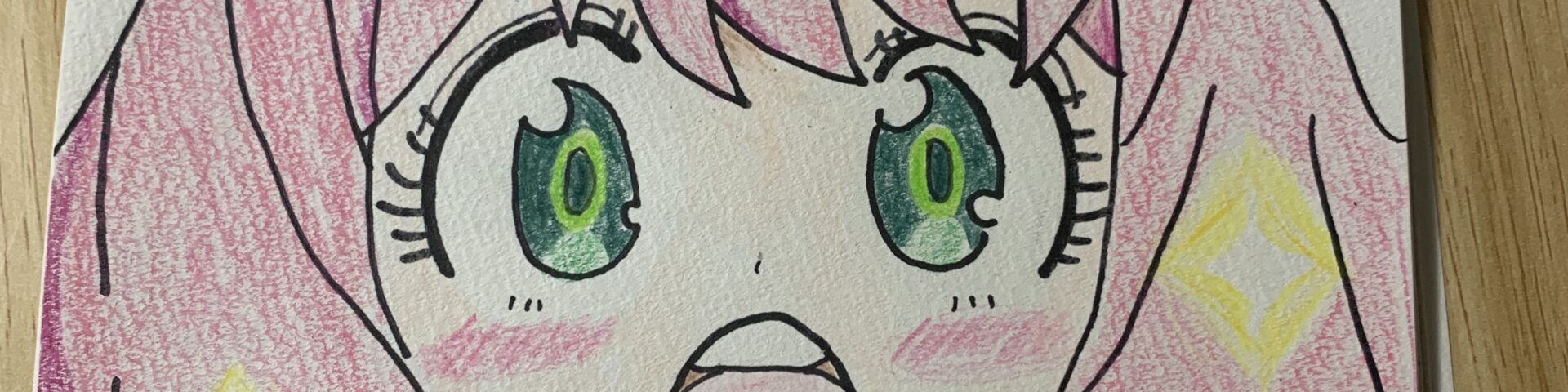子どもが何かにハマり出すと、たいてい私も影響を受け、アニメを観る機会が増えてきます。プリキュアや鬼滅の刃、呪術廻戦などは、その典型例です。あまりにもSPY×FAMILY人気がすごいと聞いたので、まずは単行本を1巻から3巻まで買いました。これは、なかなかおもしろい、そして「人権」につなげて考える内容がいくつも登場してきます。せっかくなので少しずつ読んでいこうと思うので、この後、4巻以降で「人権」について考えるエッセンスが登場したら、また書こうと思います。
ジェンダー
ロイドに与えられたミッションの一つは、アーニャを試験し合格者だけが入学できる学校に入学させることです。その面接で、ヨルはアーニャが偏食であることを伝えると、「いつもご家庭ではどんな料理を?」と面接官が「ロイド」ではなく「ヨル」に聞くシーンがあります。ロイドは「ウチは料理は主にボクが作っています」というと、もう一人の面接官が、「うっそ、飯作らない嫁とか存在するの?娘の前に自分に厳しくした方がいいよ」とヨルが言われるシーンがあります。ロイドは、ヨルのことについて「料理以外の家事や育児は申し分がない」と言うと、面接官が「いやあまあ、それはどっちも女がやってあたりまえのやつだし」と返してくるシーンがあります。読んでいて、とても腹立たしい一場面です。一人の面接官は「料理」について何故、アーニャの母役のヨルに聞いたのか、これは無意識・意識的に「女性・母の仕事・役割」という認識を有しているからに他なりません。性によって、なすべき家事や育児など決まっているはずはありません。ヨルは市役所で公務員として働き、課長ら上司にコーヒーを淹れる様子が描かれています。「女性らしさ」や「女性はこうあるべき」など意識的・無意識の思い込みや決めつけ、偏見に気づいていくための学びに活用することができます。
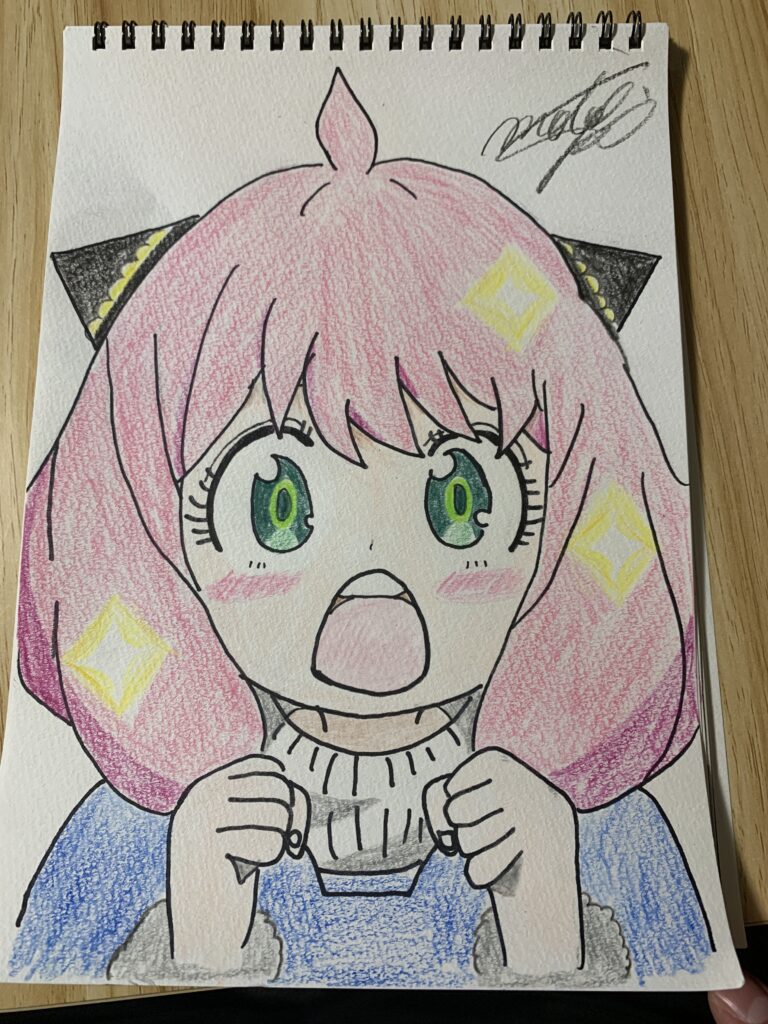
自他への「バイアス」の影響やマイノリティに不公正な社会のあり方
また、ヨルが「私ってば、ダメな母親です」というシーンがあります。するとアーニャがヨルに「アーニャ、つよくてかっこいいははすき!」と返す場面があります。「母とは、親とは、女性とはこうあるべき」というつくられた価値観で、生きづらさを感じさせられる人たちが少なくありません。こうした社会意識を内面化させられることは珍しいことではなく、それが性にはじまり、年齢についても本当は好きで着たい服ややりたい髪型、髪色などがあっても、この年齢ですべきではない、恥ずかしいことだ、周りからどう見られるかなどを意識させられ、本意ではないものを選択させられることも起きています。人は自由です。生きづらさを抱えさせ、自分を縛るものから解放されるために、社会意識やバイアスなどを学び、自他が不必要な呪縛から解き放たれることが必要であり、そうした学びに使うことができます。
第1巻でロイドが交際していた相手(スパイとして)と簡単に別れた際、「結婚?人並みの幸せ?そんなものへの執着は、スパイになった時に捨てた」という心の声が出てきます。結婚することが幸せにつながるとは限りません。人には多様な生き方があり、それを選択する権利も有しています。また、日本では同性婚が未だ認められていません。マジョリティには努力や実績とは無関係に、生まれ持って合理的な配慮が提供される社会である一方、マイノリティにとっては、マジョリティにあたりまえに認められている権利が認められていない、マイノリティに対してのみ、さまざまな制限が課せられるなど、制度的な差別、慣習や慣行としての差別などは日本社会に未だ横たわっていることとつなげて考えることができます。
「普通」とは何か
ロイドとヨルが出会い、ミッションのために、あるパーティーに出て、互いが結婚していることを証明する必要のある二人は、パーティーに参加する利害が一致し約束し合います。しかし当日、ロイドに緊急のミッションが入り、手こずってしまい、待ち合わせ時間に遅れてしまいます。待っても来ないロイドに、ヨルは仕方なく一人でパーティー会場に入ります。会場には、カップルばかりいる様子を見て、ヨルは、「家族を持ち、子供がいる、それがきっと『普通』なのでしょうね」と心で思う描写があります。ヨルのいう「普通」とは何でしょうか。結婚し、家族を持つことは普通ではなく、その選択をする人たちが「多い」というだけのことであって、それが「普通」ではありません。多数の側の行いや考えが「普通」や「正常」とは限りません。ヨルは、このようなマジョリティ中心社会の中で作られてきた「社会意識」を内面化している様子が見られ、その「普通でない」自分を否定的に捉えている姿が描かれています。「普通とは何か」を考え、自分やマジョリティの「普通」を当てはめられるマイノリティの生きづらさや抑圧などについて、加害性を有することがあることなどについて考えていくことができます。

ロイド(スパイ)、ヨル(殺し屋)、アーニャ(超能力者)のような家族構成も、本人たちにとって「普通」の家族のかたちであって、「これでないといけない」など存在しないはずです(ただし、殺し屋で人を殺傷してきたことについては当然同意していない)。マジョリティの側にあることで正常性を抱くと、マイノリティに対し「特別な存在」「意外なこと」「変わっている」などと捉える・意識することが発生することがあります。マジョリティが常に正しいわけではありません。
職業差別
また、ロイドが「イケメン」であることに嫉妬したパーティー参加者が、ヨルが市役所に入る前、「いかがわしい仕事をしていたらしいわよ。男の人に呼ばれて、マッサージするんでしたっけ?やらしい」と言われ、本当は鍼灸マッサージと謳った刺殺の仕事であったが、そのことをヨルは言えるはずもありません。ヨルは、ロイドに「違うんです。ロイドさん」というと、ロイドは「素敵です。ヨルは両親を早くに亡くし、幼い弟を養うために必死で頑張ってきました。自分を犠牲にしてでも。誰かのために何かのために過酷な仕事に耐え続けることは、なみの覚悟では務まりません。誇るべきことです」と言うシーンがあります。職業に対する差別は残念ながら確かに存在し、コロナ禍の国による給付を巡っても、国の恣意的な判断で風俗店などは救済の対象外にさせられるなど、制度的な職業差別も明らかになりました。

「子どもの権利」
ロイドに与えられたミッションの一つは、アーニャを試験し合格者が入学できる学校に入ることです。面談で、学校の教師がアーニャに対し「今と前の母親とどちらが良いか」とアーニャに質問し、無理やり答えさせようとします。アーニャは動揺し、涙を流します。その教師の発言に、ロイドは「子どもの気持ちを軽んじるのが貴校の教育理念なのでしたら、選ぶ学校を間違えました」と反論しました。「子どもの権利」が軽んじられる状況が実際の学校現場でも起きています。校則に生徒の人権を侵害するものがいくつもあります。「地毛証明書」の提出の強制、黒髪の強要、男女別の頭髪や服装の規定、「生徒は自宅から学校に通うことが原則です」「手弁当は非行の防止につながる」など、アーニャのように児童養護施設から学校に通う生徒はいない存在として扱うような内容など、深刻なものが多数存在していました。形上、校則からは消えましたが、人々の中に、身近に出会う人たちの中に、アーニャのような環境で育つ・育ってきた人たちがいるという前提を持って接することができている人は少ないように実感しています。知らないこと、さまざまな条件を有する人が身近にいるかもしれないなど、兼ね備えておくべきことができないことで、マイノリティに疎外感を与えたり、侮辱的なメッセージを送ってしまうことなどにつながることがあります。アーニャが置かれてきた・置かれている状況から「子どもの権利」につなげて考えることができます。
ダミアンから考える「マジョリティの特権」
アーニャが学校に入学すると、ロイドがスパイの対象としている資産家などの子どもたちも入学しており、そこに「ダミアン」という資産家の子どもが登場します。

アーニャは、ダミアンを「じなん(資産家で生まれた二人めの子どもであることを心の声などで知ったため)」と呼んでいます。アーニャがダミアンと出会った時、ダミアンは、アーニャに「フン。なんだ大したことないな。どうせショボい資産なんだろ」と言い、ダミアンの仲間も「庶民はほんと図々しいですねぇ」というシーンがあります。ダミアンやその仲間は、努力や実績を積み重ねたから、資産家という経済的にとても裕福な家庭に生まれ育ったわけではありません。それは「偶然の賜物」です。生まれ持って、家庭が経済的に裕福であること、保護者がいる環境で生まれ育つこと、保護者が4年大学を出ていること、勉強を教えてもらえる環境がある・学習塾に通える環境にあること、虐待を受けたことがないことなどは、この社会でたいてい優位に機能します。こうした、個人の努力や実績とは関係なく、偶然持ち得た属性・条件がマジョリティ側に多くあることによって、自動的に得られるあらゆる恩恵や優位性のことを「マジョリティの特権」と言います。
マジョリティは権力を有し、それを行使する特権も持っており、それは差別や人権侵害を停止させたり是正したりするための仕組みをつくることができるといったことや、差別を受けている・受ける可能性のある、経済的・文化的・社会的に不利な立場に偶然置かれたマイノリティに問題解決の責任を負わすのではなく、マジョリティがマジョリティの責任で問題解決に取り組む責務があることなどとつなげて考えることができます。
「ルッキズム」
ダミアンとその仲間は、アーニャのことを「ブス」「ドブス」「短足」など、見た目で中傷するような発言を何度も言うシーンがあります。ルッキズムに及ぶシーンが何度も登場します。容姿を侮辱する言動だけがルッキズムではなく、「身長が高くていい」などや「美人アスリート」という報道などについても、つくられた社会意識に影響され、肯定的に評価している「つもり」の言動が、相手や周囲に被害を与えるような問題も起きています。人が選択できない容姿に関し、肯定的に評価することが、必ずしも相手が喜んでいるとは限りません。私は身長が183センチありますが、目立つのが好きな方ではない性格で、幼少期に「そんな大きな体をしているくせに、泣くな」などを言われて育ってきています。個人の内心で思うことは自由ですが、それがどのような場で発するかによって、肯定的なメッセージでも相手が喜ぶとは限らず、むしろ被害を与えることもあること、「イケメン」「美人」と特定の人物に主張することで、周囲に対して「イケメンや美人ではない」というメッセージにつながってしまうことがあるということを知る必要もあり、そうしたことを学ぶことができます。
(好意的)セクシズムや関係の非対等性
学校の体育の授業では、ドッヂボールをするシーンがあります。アーニャたちと対抗する別のクラスには、大人のような体格の生徒がおり、とてつもないパワーで、凄まじいスピードのボールを投げる生徒が登場します。あまりにも豪速球なので、アーニャの友だちは「ちょっと!あんなの当たったら死んじゃうし!」と言うと、その生徒は「安心しろ。女子には手加減する」と返します。アーニャの友だちは「それはそれで、なんかムカつくー!」と言いながらボールを投げました。ボールはいとも簡単にキャッチされてしまいます。ここで考えたいのは「『女子』だから手加減が必要なのか」ということです。相手の体格や身体の状態によって判断するものを「女子」という属性に対して手加減が必要だと認識しているということです。
「女性には優しく接するべき」と好意的な考え方に捉えられがちですが、では、アーニャの友だちは何故そう言われて怒ったのでしょうか。関係性が非対等である、男子から女子は下に見られている、守られるべき弱い存在として扱われているということです。つまり、女性に対する侮辱的なメッセージになっているということを認識する必要があります。セクシズムに限らず、「障害」者に対しても「権利の主体」のはずが、「保護の対象」と捉えてしまうことが少なくありません。小学生からは「できることが少ないので、かわいそう」という非対等性を兼ね備えた発言をよく聞きます。孤児院で生活するアーニャのような子に対して、保護者と離別した生活を送る子に対して、「かわいそうな存在」という同情心を抱かされる子どもたちも少なくありません。本人たちは自分のこと、自分の暮らしのことをどう捉えているかが置き去りにされてはなりません。無意識に抱く非対等性を自覚するとともに、どう克服していくかなどについて考えていくことができます。

「・・・本音を隠し、本性を隠し・・・」
SPY×FAMILYの第一巻の冒頭で「人はみな誰にも見せぬ自分を持っている。友人にも恋人にも家族にさえも。張りつけた笑顔や虚勢で本音を隠し、本性を隠し、そうやって世界はかりそめの平穏を取り繕っている」という内容が登場します。
例えば、差別や人権侵害を受けること、マイノリティ性や悩み事・困り事、コンプレックスなどを知られると差別的な扱いを受けるのではないかと不安を感じたり、そのことを知った相手との関係性や距離感に悪い形への変化が生じるのではないかなどを抱かされることで、本当の自分を隠す、自分にとって大切なことを誤魔化すような生き方を強いられている人たちとつなげて考えることができます。誰なら、どのような人なら安心して自分を出せるのか、どうすれば、本音で、本当の自分で生きることができるのか、そのために何をなす必要があるのか、反差別の仲間づくりを考えていく上でも活用できる内容です。
一人ひとりのバックグラウンド
ロイドは、アーニャを引き取りはじめた時、アーニャが泣いている様子を見て、「そうか。子どもが泣いていると腹が立つ理由が何となくわかったぞ。」と心で言い、「誰も救いの手を差し伸べてくれない孤独や絶望と、ただ泣くことしかできなかった無力感。捨て去ったと思った過去の自分と無意識に重ねていたのだな。いや、それどころか」というシーンがある。そして、「子どもが泣かない世界。それをつくりたくて、俺はスパイになったんだ」と、バックグランドの一端が垣間見えるシーンがあります。そして、アーニャは「孤児院(児童養護施設)」で生活していた子であり、ロイドがミッションをクリアするために子どもとして選んだ子であり、3巻までのストーリーでは、ロイド・ヨル・アーニャともに、その経緯やバックグラウンドは不明です。ちょっと嫌だったのは、孤児院の職員が、あまり子どもたちを大切にしている人ではないという描かれ方です。子どもたちを大切に思い、施設での生活が豊かになるように、子どもたち同士の関係性を丁寧に繋いでいったり、休みの日に遊びに出かけるなどして、生活体験を豊かにしようと取り組んでおられる職員さんたちがいます。意地悪な職員という描き方でなくてもよかったはずと残念に思っています。施設のことや職員を知らない子どもたちが、ステレオタイプを抱かないか、少し心配です。
ロイドは「精神科医」、ヨルは「市役所で働く公務員」、アーニャは「小学生」が表向きであり、裏側ではロイドは「スパイ」、ヨルは「殺し屋」、アーニャは「超能力者」です。身近な人たちに置き換えて考えてみると、私たちが普段、接している人たちにも、その人が普段、表している姿がすべてではなく、マイノリティ性を有しているかもしれない、表向きの姿の裏側に悩みや困り事、コンプレックスなどを抱かされているかもしれないといったことと重ねて考えることができます。「見えることから得られることは限られている」ということです。それは、マイノリティに対するアファーマティブアクションに対し「逆差別だ」などと主張する人たちが一定数いる中、現象面だけ捉えれば、そのような考え方に及んでしまっても、その政策が何故必要なのか、そもそもマジョリティとマイノリティとで社会の中の立ち位置や置かれている状況など何がどのように違うのかなど、「見える」政策から、その理由まで捉えていこうとすることが重要であり、そうしたことともつなげて考えることもできます。
この後、4巻以降、読み進めていく中で、人権に関する内容が出てきた場合、またPart2を書いていきたいと思います。ご覧いただき、ありがとうございました。